「お寺でお願いしてはいけないって本当なの?お寺の参拝でしてはいけないことや願い事の事例が詳しく知りたい!」
幼い頃に家族でお寺を参拝した際、願い事をしないようにと家族から教わったという人も中にはいるでしょう。
だからこそ、お寺の参拝マナーはしっかりと守って、バチが当たらないようにしたいと考えているかもしれません。
そのため、このような疑問を持っている方も多いのではないでしょうか。
- お寺でお願いしてはいけないの?
- お寺の参拝でしてはいけないことは?
- お寺の参拝の願い事の事例はある?
そこで今回は、お寺の参拝でお願い事をしてはいけないのか詳しくお伝えします。
また、お寺の参拝で願い事以外に守るべきルールも紹介しますので、お寺へお参りに行く予定がある人はぜひチェックしてみてください。
正しいマナーを理解し、仏様のご利益を受けられるような参拝を心がけましょう。
お寺でお願いしてはいけないって本当?お願いしてはいけない理由は?

結論からお伝えすると「お寺でお願い事をするのはNG」という話はあくまで噂です。
なので、参拝で仏様にお願いをしたからといってバチが当たるわけではありません。
では、どうしてこのような言い伝えが広まったのでしょうか。
ここからは、お寺でお願い事をしてはいけないと言われていた理由や、お願い事をする際の注意点について詳しくお伝えします。
- かつてお寺がお願い事をする場所でなかったのは事実
- お寺で願い事をしてはいけない理由
- 現在はお寺でお願いしても良い
- お願いする場合は謙虚な姿勢を心がける
- お願いしてはいけないお寺もある
かつてお寺がお願い事をする場所でなかったのは事実
実はお寺は、かつてお願い事をする場所ではありませんでした。
きっとその話が語り継がれた結果、今日も「お寺ではお願い事をすべきではない」と言われることがあるのでしょう。
現在はお葬式や法事のためにお寺へ足を運ぶ人も少なくないかもしれませんが、お寺が先祖供養を始めたのは江戸時代ごろの話です。
つまりお寺の信仰対象である、仏様が説いたものではないのです。
お寺のそもそもの建立の目的は、出家をした僧が学んだり寝泊りをしたりするためだと言われていました。
そのため、お寺でお願い事をするのは筋違いだと考えられるようになったのでしょう。
お寺でお願い事をしてはいけないと言われていたのはなぜ?
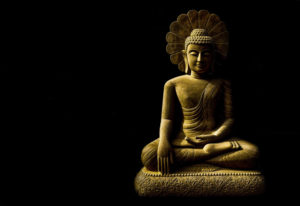
お寺でお願い事をすべきでないと考えられていたのは、やはり建立の目的が異なるためです。
お寺には本来、僧たちが学びを得る寺子屋や地域の福祉や文化の拠点としての役割がありました。
それが、葬儀や法事に使われるようになったのは江戸時代になってからです。
そのためお寺へ参拝するのは、仏様に日頃の感謝を伝えたり煩悩を絶ったりするためだと考えられていました。
葬儀を無事終えられたことを報告するために、お寺へ参った人も多かったと言われています。
かつては御朱印集めやパワースポット巡りといった趣味、初詣などのイベントではなく宗教的な意味合いで参拝する人が多かったのです。
現在はお寺でお願いしても良い場合がほとんど
仏様にお願い事をすること自体は決して悪い行いではなく、現在は認められているケースが大半です。
昔からの言い伝えを大切にしている人にとっては違和感があるかもしれません。
ですが、近年は願い事をする際の立ち振る舞いについて指南するお寺もあります。
ちなみに天台宗や真言宗などの、密教系のお寺は基本的にお願い事をしても良いとされています。
たとえば、東京の浅草寺や千葉の成田山、神奈川の川崎大師などは初詣の時期を中心に多くの人で賑わっているでしょう。
これらのお寺はいずれも密教系です。
ただし中には例外もありますので、お願い事をしたい時は参拝前にお寺へ確認することをおすすめします。
またお願い事がOKだからといって、何でも叶えてもらえるわけではありません。
このあと紹介するルールやお参りの手順を踏まえた上で、適切な所作を取るよう心がけましょう。
お願いする場合は謙虚な姿勢を心がける

お寺でのお願い事には「仏様に見守ってもらいつつお力添えをいただくために誓いを立てる」という意義があります。
つまり「仏様にお願い事を叶えてもらう」というよりは「自分自身の力で望みを叶える」という意味合いが強いです。
お寺でお願い事をする際は、ルールやマナーを守って謙虚な姿勢で参拝することを心がけてください。
謙虚な姿勢で参拝することは、仏様へ敬意を示すことにも繋がるでしょう。
お願いしてはいけないお寺もある
お寺でお願い事をするのは基本的に認められていますが、宗派によってはお願い事をしてはならないお寺も存在します。
特に、禅宗や浄土真宗などの曹洞宗ではお願い事をするのが認められていないケースが多いので注意してください。
禅宗は「自力本願」の考え方を大切にしています。
つまり、自らが修行をして身につけた力で願い事を叶えるべきだとされているのです。
浄土真宗の考え方である「他力本願」は一見仏様のことを頼りにできそうな印象に思えるでしょう。
ですが、ここで言う他力本願は本来と異なる意味を持っているので要注意です。
自身の勘違いでマナー違反を犯さないためにも、やはりお寺でお願い事をする際は参拝前に確認するのが適切と言えるでしょう。
お寺の参拝でしてはいけないことは?守るべき10のルールを紹介

ここからは、お寺で参拝する際にしてはならない10のルールをご紹介します。
仏様を怒らせないためにも、参拝時のタブーをしっかりと理解した上でお寺を訪れてみてください。
直近でお寺を参拝する予定がない人も、この機会に知っておけば後々役に立つ日が来ますのでぜひチェックしておきましょう。
- 毛皮や革製品を身につけること
- ペットを連れていくこと
- 日が暮れてからお寺を訪ねること
- 門の敷居を踏むこと
- 鰐口(わにぐち)を鳴らし過ぎること
- 他人の不幸を願うこと
- 合掌の際、拍手すること
- 縁起の悪いお賽銭金額を用意すること
- お参り前に授与品をいただくこと
- お参りの後に鐘をつくこと
毛皮や革製品を身につけること
まず服装については、毛皮や革製品を身につけて参拝してはなりません。
仏教では命がある生き物を故意に殺してはならないという教えがあり、毛皮や革製品は殺生をイメージさせるためです。
フェイクファーやドクロがついた服、アクセサリーなども念のため着用を避けた方が良いでしょう。
ほかには露出の多い服、Tシャツにサンダルなどのカジュアルすぎる服装を避ければOKです。
手持ちのアイテムで適切なコーディネートを考えてみてください。
また、お寺に行くからといって無理に正装をする必要はありません。
ペットを連れていくこと

お寺は、神聖であり清浄とされる場所です。
そのため「穢れ」とされるものを持ち込むことは、基本的にタブーだと考えられています。
特に仏教の世界においては、死体を荒らすことから野犬などの生き物を「穢れたもの」として扱ってきた歴史もありました。
そのため、犬を含むペット同伴での参拝をお断りしているお寺は少なくありません。
近年はすべての命が尊ばれ、ペットも家族の一員として認められる風潮があります。
ですが、躾やフンなどの安全面や衛生面は懸念材料として残っています。
仮に同伴OKのお寺であったとしても、キャリーに入れる必要があったり鳥居の中は同伴できない等のルールがあるかもしれません。
もちろん、一昔前に比べるとペットの同伴は寛容になりつつあります。
ですが、必ず参拝したいお寺の情報を確認した上で足を運ぶようにしてください。
もしペットを連れて参拝する場合は、ほかの参拝者の迷惑とならないようにきちんとマナーを守りましょう。
日が暮れてからお寺を訪ねること
お参りに行くのは、お寺ごとに決められた参拝時間内であればいつ行っても構いません。
しかし一般的には、日の光が差し込む午前中に行くのがベストでしょう。
心地良い光と風に当たることで、晴れやかな気分でお参りができるはずです。
やむを得ず日が暮れてから参拝する際は、石段などで転倒しないよう足元に注意することが大切です。
時期によっては虫やヘビが出ることもありますので、くれぐれも気をつけるようにしてみてください。
門の敷居を踏むこと

参拝した際に門をくぐると思いますが、門の敷居を踏むことは絶対にNGです。
お寺という場所は仏様が住んでいる「神域」です。
そのため、総門(大門)や山門(中門)などの門によって私たち人間が住む俗世と神域は別れているという考え方がありました。
門の下に敷かれた横木は、ただの敷居ではなく結界としての役割があります。
踏んで通ることによって神聖な場が汚れてしまうのです。
また建築的な見方をすれば、敷居は建物の建付けにおいても重要な役割を果たす構造部です。
多くの人が踏んで通ることにより、建物にゆがみが生じて傾いたり損壊したりする恐れがあるでしょう。
参拝のマナーとしてはもちろんのこと、長年大切にされてきたお寺を守るためにも敷居はまたぐことを徹底してください。
「敷居を踏んではならない」というのはお寺に限った話ではありません。
そのため、日頃から部屋の敷居や畳の縁を踏まないよう気をつけておきましょう。
鰐口(わにぐち)を鳴らし過ぎること
お寺の参拝では、本堂へ着いたら賽銭をおさめて鳴り物を振り動かし音を出します。
鐘楼がある場合は鐘を撞木でついたのち本殿へ向かいますが、お寺で音を出すのはいずれも仏様に挨拶をするためです。
つまり、必要以上に大きな音を鳴らすのは品格に欠ける行為と言えるでしょう。
これは、お寺の軒先などに吊るされた鰐口も同様です。
鰐口は紐を振ってもなかなか大きな音が出ませんが、鳴らし過ぎる必要はありません。
神社では鈴を思いっきり鳴らすことで邪気を払えるとされており、混同しやすいポイントなので注意しましょう。
他人の不幸を願うこと

お寺でお願い事をするのは決してタブーではありません。
ですが、他人の不幸や誰かを貶めるような願い事をするのは厳禁です。
恋愛や仕事で障壁となる相手がいたとしても、第三者の不幸や失敗を願うことはないようにしてください。
誰かを傷付けるようなお願い事は、いつか自分に返ってくるのでくれぐれも気をつけましょう。
「今のプロジェクトがうまくいくよう頑張ります」など、ポジティブ変換しつつ誓いを立てる形で願うのがポイントです。
合掌の際、拍手すること
神社と違い、お寺では手を合わせる時に音を出してはなりません。
手をパンパンと叩く柏手ではなく、胸の前で静かに手を合わせて合掌をするのがお寺で守るべき参拝マナーの一つです。
つい音を出したくなるかもしれませんが、失礼な作法に該当するので注意してください。
縁起の悪いお賽銭金額を用意すること

お賽銭の金額にルールや決まりはなく、一番大切なのは参拝者の気持ちです。
しかし、以下のようなお賽銭金額は縁起が悪いという考え方もあるので要注意です。
- 10円:縁が遠ざかる
- 65円:ろくな縁がない
- 75円:なんの縁もない
- 500円:硬貨の中で最も大きな金額であるため「これ以上の効果(硬貨)がない」と捉えられる
10円や500円は、これまで実際にお賽銭としておさめたことがある人もいるかもしれません。
財布の中にある硬貨をすべておさめているスタンスの人は、65円や75円とならないよう気をつけましょう。
ちなみに縁起が良いとされるのは「5円」「11円」「15円」「20円」「45円」で、いずれも語呂の良さが由来となっています。
いざ参拝をする時に適切な小銭がなく焦ってしまわないよう、事前にお賽銭としておさめる小銭を用意しておくのがおすすめです。
お参り前に授与品をいただくこと
お寺に足を運んだ際、お参りの前に授与品や御朱印をいただいていませんか。
実はこれもマナー違反の一つで、仏様の御魂や功徳が込められた授与品やご縁を象徴する御朱印はお参りのあとにいただくのが適切です。
日常生活においても、挨拶をしないまま何かをもらおうとするのは失礼にあたります。
まずは心を込めてお参りをしたのち、授与品や御朱印をもらいに行くよう心がけてみてください。
これは神社にも共通するマナーですので、ぜひ押さえておきましょう。
お参りの後に鐘をつくこと

先ほども紹介した鐘楼は、比較的大きなお寺にのみ存在します。
鐘は鰐口と同様に仏様へのご挨拶として鳴らすものなので、お参りの前に足を運ぶことを徹底してください。
お参りの後に鐘を打つ「戻り鐘」は、功徳が消え失せるという考え方もあるので気をつけましょう。
お寺での願い事の事例は?具体的なお願いの仕方を解説

お寺でお願い事をする場合は仏様に願い事を叶えてもらうのではなく、仏様の前で誓いを立てることに意味があると考えることが重要です。
謙虚な姿勢を心がけつつ、仏様に敬意と感謝の気持ちを持ってお願い事をしてみてください。
お寺でお願い事をするにあたって忘れてはならないのが、仏様を困らせないよう自分自身の住所と氏名を伝えることです。
仕事に関するお願い事をするのであれば、勤務先もあわせて伝えておくとよいでしょう。
具体的なお願いの仕方については以下の通りです。
「(住所)に住んでいる(氏名)です。○○が実現するよう頑張りますので見守っていてください」のような形です。
間違っても「~してください」「~しますように」と、仏様に乞うお願いの仕方はしないよう気をつけてください。
まとめ

ここまで、お寺の参拝でお願い事をしてはいけないのか詳しくお伝えしてきました。
- お寺でお願い事はして良い
- ただ一部NGなお寺もある
- 事前に調べておくことが大切
- マナーもあるのできちんと守ること
- お願いの際は名前も伝えよう
かつてお寺でお願い事をするのはタブーだと考えられていましたが、近年は多くのお寺で認められています。
ただし、宗派やお寺ごとにルールが異なるので事前に確認してから足を運ぶようにしてください。
そしてここまでお伝えした参拝時のマナーや参拝方法に気をつけながら、仏様に誓いを立てる形でお願い事を伝えましょう。
参拝に関して困りごとや不安が残る場合は、お寺に直接確認してみることをおすすめします。
